レッスン内容
・基礎練 A線D線でのポジション練習
・ソナタホ短調 マルチェロ
・基礎練 A線D線でのポジション練習
ホ短調の練習でドレミの塊などを意識して練習する。
位置関係をそれぞれの距離感で覚えるのではなく、
それぞれ独立して覚えるようにする
・ソナタホ短調 1楽章
11小説目のところのクレッシェンドの入り方 小さくして入る
ときどき音程が上がるにつれて音量が上がるときがあるので注意
13小説目以降の音の大きさ 小さくしない 抜けないようにする
最後の小説のトリル後のミはかなりゆっくりと貯めて貯めて最後の音に繋げる
クレッシェンドの最後の2音くらいで最大の大きさにする
音のメリハリをつける
第二楽章の入りの音が抜ける時がある
入り方で弓はちゃんとおいて始める
タクトの頭を意識してそこにあった音を出す
通しでやりすぎるのはダメ
部分的に取り出してそこから始められるような状態にする
どこで始めてもできる状態にする
(極端に変なところから始めても良い)
移弦をするときに前の音が混ざるから混ざらないようにする
しっかり一音ずつ発音する練習をする
26小説目のピアノのところの音が高くなるところ(シミ)が
音の大きさが安定していない 小さくない
拍の頭を意識することが大事
怖いところ 不安なところを具体的に表せるようにしておく
そしてそれを克服するために練習もする
ぼんやりと不安があると緊張する原因になる
まとめ
やはり細かなところを気にすると色々な課題が見えてくるのがよくわかったレッスンになりました。
次回からのレッスンでは発表会の合奏曲も練習していくので
ソナタの練習が雑にならないようにやっていく必要がある。
今回のレッスンや前回のレッスンで共通して言えそうなところは
音の強弱に関しては毎回気を付けて練習しないと、
変な癖がついてなかなかその癖を解消しにくくなってしまうこと。
そのためにも部分的な練習をしていき、
その場所にあった音をイメージして練習する必要があると思った。
音程に関しては、その日の初めにポジションの練習を少しずつし、曲の中でも精度を高めれるように違和感を感じたら戻って確認して次の練習に移るようにしたい。
来週のレッスンに向けて頑張るぞ〜!
(練習できそうな日が少ないけれど。。。。)
この記事を読んでいただきありがとうございました!
他の記事も読んでいただけると嬉しいです!
ではまた会いましょう!ブラストでした〜!
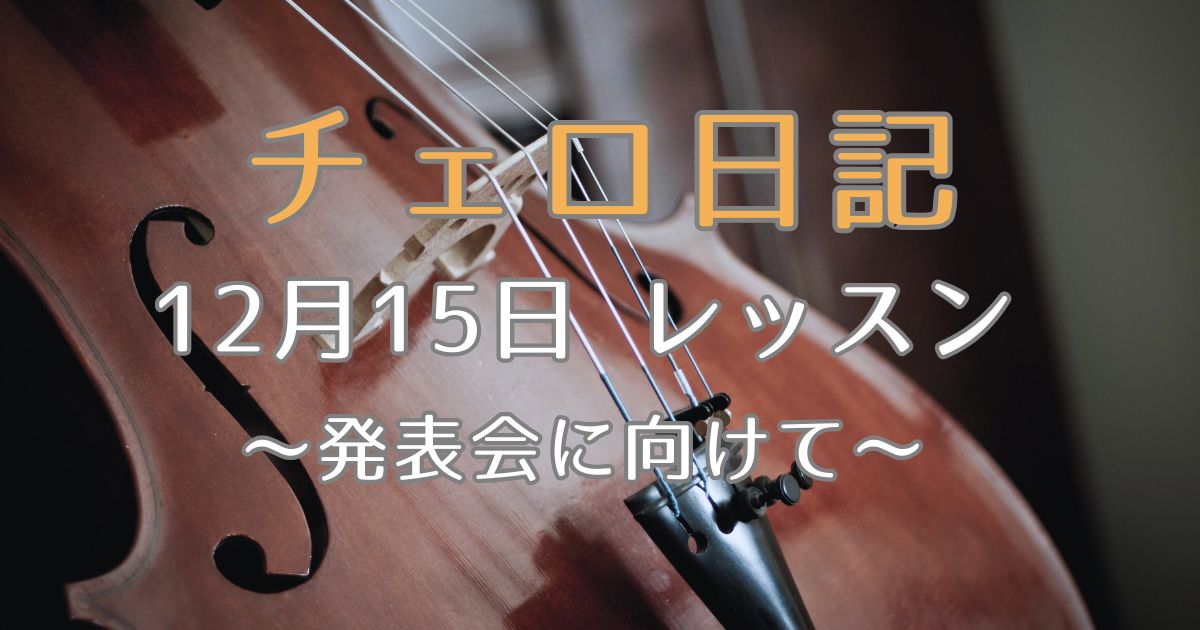
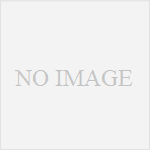
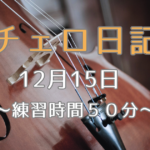
コメント